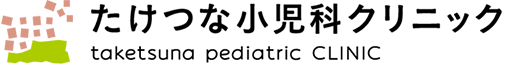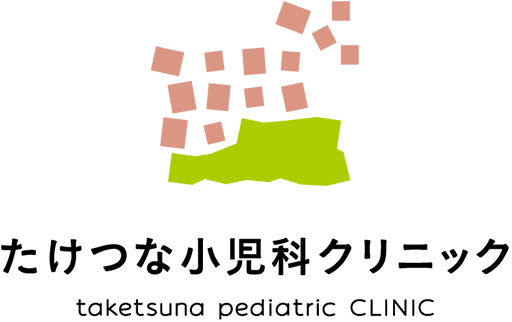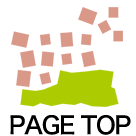婦人科でのピルのもらい方をわかりやすく解説!費用・種類・高校生の処方方法も

ピルを初めてもらうために婦人科を受診したいけれど、「どんな流れで診察が進むの?」「高校生や未成年でもピルだけもらえる?」など、不安や疑問を持つ人は少なくありません。

初めて婦人科を訪れる方でも迷わずスムーズにピルを処方してもらえるよう、よくある疑問や不安も丁寧に解消していきます。
婦人科でピルをもらう方法
ピル処方の基本
ピルは婦人科や産婦人科で処方される経口避妊薬(飲み薬)であり、生理痛の緩和や生理不順の改善、避妊目的など幅広い用途で使われます。しかし、処方を受けるには医師による診察や検査が必要で、特に初めての方は不安を感じることも多いでしょう。この記事では、婦人科でのピルのもらい方を詳しく解説します。
産婦人科でピルだけもらうことは可能?
婦人科・産婦人科では、ピルだけをもらうことも可能です。ネット上では、「診察や検査なしにピルだけ欲しい」という声が多くありますが、初めて処方を受ける場合は原則、簡単な診察や問診が必要となります。医療機関によって方針が異なるため、受診前に電話や公式ホームページで確認しておくと安心です。
特に、「産婦人科 ピルだけもらう高校生」というニーズも増えていますが、高校生や未成年でもピルの処方は可能です。ただし、保護者の同伴や同意が求められる場合があるため、各クリニックに事前確認が必要です。
【ポイント】
・ピルのみの処方は多くのクリニックで可能
・初回処方の場合は簡単な診察・検査がある場合が多い
・未成年や高校生も処方可能(条件は病院によって異なる)
ピル処方時に婦人科に伝えるべきこと
婦人科受診時に以下の内容を医師に伝えると、より適切な処方を受けられます。
- 現在服用中の薬・サプリメント
- アレルギーの有無(薬品アレルギー、食品アレルギー等)
- 持病や治療中の疾患の有無(血栓症、肝疾患、乳がんなど)
- 喫煙習慣の有無(喫煙者は副作用リスクが高まるため重要)
伝える内容を事前に整理しておけば、スムーズに診察が進みます。
ピル処方時に持っていくと便利なもの
診察をスムーズにするため、受診時に次の持ち物を準備しておくと良いでしょう。
- 健康保険証
- 現在服用中の薬やサプリメントの情報
- 生理周期の記録(アプリやカレンダーで記録したもの)
- 服薬に関する質問メモ
【持ち物リスト】
| 婦人科受診時の持ち物リスト | 優先度 | 理由・補足説明 |
|---|---|---|
| 健康保険証 | 必須 | 保険診療を受けるため必須 |
| お薬手帳・薬情報 | 他薬との飲み合わせチェック | |
| 生理周期記録 | 正確な診察・薬の選定に役立つ | |
| メモ(質問事項) | 医師への質問漏れを防ぐ |
産婦人科でピルだけもらうことは可能?
婦人科や産婦人科でピルだけもらうことは可能ですが、初診時は問診や簡単な検査が必要な場合が多いです。
近年、産婦人科にピル処方のみを希望して訪れる人が増えており、特に高校生や未成年者からは、「ピルだけ処方してもらえるか不安」「診察や検査が恥ずかしい」といった声も多く見られます。実際に高校生でもピルだけもらえるケースは多く存在しますが、病院によって対応が異なります。
厚生労働省によると、避妊を目的とした低用量ピルの利用者数は年々増加しており、特に10~20代の若年層で需要が高まっています(厚生労働省「経口避妊薬(ピル)の使用実態調査」2022年)。
実際の事例では、「初めてピルをもらいに婦人科を訪れたが、問診票を書き、診察は約5〜10分程度で終了し、その後すぐにピルが処方された」というケースもあります。
一方で、未成年や高校生の場合、親の同意書が必要な病院と不要な病院があります。親の同意を得にくい場合、親の同意が不要な医療機関を事前に調べておくとよいでしょう。
■高校生向け:ピル処方時の保護者の同意の要否(例)
| 病院名(所在地) | 親の同意の有無 | 備考・補足 |
|---|---|---|
| Aクリニック(東京) | 不要 | 16歳以上は同意なしで処方可能。 |
| B病院(大阪) | 同意書が必要 | 事前に公式サイトで書式ダウンロード可 |
| Cオンライン診療(全国) | 不要(電話確認あり) | 初診時に電話で簡単な確認を行う |
※上記はあくまで一例です。病院ごとに対応が異なるため、必ず受診前に公式サイトや電話で確認を行いましょう。
婦人科や産婦人科でピルだけをもらいたい場合は、予約時や受付時に「ピルの処方だけを希望しますが、診察や検査は必要ですか?」と質問すると、スムーズな受診が可能です。
【ポイントまとめ】 ・初回処方時は簡単な問診・検査があるケースが多い ・未成年は同意書の有無を事前確認 ・全国の病院で対応が異なるため、事前確認が重要
ピルだけもらうために婦人科を受診した際の具体的な会話例・流れ
婦人科でピルだけを希望する場合、実際にどのような流れで診察が進むのか不安な方も多いでしょう。ここでは、婦人科でピルをもらう際の具体的な会話例と、診察の流れを詳しくご紹介します。
【診察の流れと具体的な会話例】
- 受付での流れ 受付で「ピルの処方を希望しています」と伝えます。受付のスタッフから問診票を渡されるため、記入後に提出します。
【問診票でよくある質問内容】 ・初経の年齢、最近の生理周期 ・既往歴(持病や過去の病歴、手術歴) ・喫煙習慣や服薬状況(飲んでいる薬・サプリメントなど) - 診察室での医師との会話例 医師との会話は以下のように進むケースが一般的です。
【医師との具体的な会話例】
| 会話の流れ | 医師側の発言例 | 患者側の発言例 |
|---|---|---|
| 処方希望の確認 | 「今回はピルを希望されていますね。理由を教えていただけますか?」 | 「避妊目的です」「生理痛が辛いためです」など |
| 服薬経験の確認 | 「これまでにピルを服用したことはありますか?」 | 「ありません。初めてです。」 |
| 副作用の説明 | 「服用中、最初の数か月は吐き気や頭痛など軽い副作用が出る可能性があります。」 | 「副作用が出た場合、どうすれば良いですか?」 |
| 希望ピルの確認・選択 | 「避妊目的ならこのピルが使いやすいですが、ご希望はありますか?」 | 「費用が安めのピルを希望します。」 |
| 血栓症リスク等の確認 | 「血栓症のリスクがあるため喫煙や肥満、高血圧などの確認をします。」 | 「喫煙はしません。血圧は正常です。」 |
このように具体的な会話例を把握しておけば、初めて婦人科を受診する際にも安心です。
【診察後の流れ】 医師の診察後、薬の説明を受け処方箋を受け取ります。その後、病院内もしくは近隣の薬局でピルを受け取り、終了となります。
最近では、院内で直接薬を処方してくれる病院も多く、診察から薬の受け取りまでがスピーディに行える施設も増えています。
処方までの具体的な流れ(予約〜受け取りまで)
婦人科でピルをもらう際の具体的な流れを、初診時の予約から薬の受け取りまで順を追って説明します。「婦人科 ピル もらい方」の流れを理解しておくことで、当日の不安を軽減し、スムーズな処方につながります。
【STEP1】病院を選び、予約する
まずはピルの処方をしている婦人科・産婦人科を探します。インターネット検索や口コミを参考にすると、自分に合った病院が見つかります。特に初診の場合、予約制の病院が多いため、電話やWeb予約をしてから来院しましょう。
【予約時に確認しておきたいポイント】 ・ピルのみの処方が可能か ・予約は必要か(当日飛び込み受診可能か) ・初診時に必要な検査や費用の目安
【STEP2:受付~問診票記入】
当日は受付後、問診票を記入します。ピル処方目的で受診した場合、問診票の質問内容は比較的シンプルで、生理の周期や既往歴、副作用のリスク因子(喫煙歴・肥満・高血圧など)の確認が中心です。
【問診票で聞かれる主な項目】
- 年齢、生年月日
- 最終月経日
- 生理周期や痛みの有無
- 妊娠経験・出産経験の有無
- 持病やアレルギー、服薬中の薬について
- 喫煙や飲酒習慣の有無
【STEP2】医師による診察と検査
問診票記入後、診察室に呼ばれます。診察は医師との面談形式が一般的で、婦人科検診(内診)はピル処方目的の場合は必須ではありません。ただし、病院によっては血圧測定、体重測定、血液検査(血栓症リスク確認)を行うことがあります。
【初回処方でよくある検査】
- 血圧測定
- 体重測定
- 血液検査(血栓症リスクや肝機能の確認)
- 場合により内診(病院による)
※日本産科婦人科学会では、ピル処方にあたり内診は必須ではないとしていますが、医療機関によっては推奨するケースもあります。
【STEP3:ピル処方(薬の選択)】
診察・検査終了後、医師が患者の体調や目的に合わせてピルの種類を提案します。ピルの種類や副作用の説明を受けた上で、処方を受けます。
【処方時に確認しておきたいポイント】 ・薬の種類(低用量ピル、超低用量ピル、ミニピルなど) ・副作用が出た時の対処法 ・飲み忘れ時の対処法 ・定期検診の頻度(多くは半年〜1年ごとに検査)
【STEP4:薬の受け取り】
処方箋を受け取ったら、院内の薬局や、外部薬局でピルを受け取ります。最近では院内処方の病院が多く、診察後すぐに薬を受け取れる場合もあります。
【薬の受け取り時の注意点】
- 薬の用法・用量を必ず確認
- 次回受診日や再処方方法を確認
- ピル服用時に注意する生活習慣(喫煙・アルコールの制限など)
■婦人科でピルをもらう流れまとめ(予約~薬の受け取りまで)
| STEP | 項目 | 内容(具体的な対応) | 備考・所要時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 予約(電話・Web) | ピル処方可能な病院を探し予約。 | 約5〜10分(当日予約も可能な病院あり) |
| 2 | 受付・問診票の記入 | 生理周期や服薬状況、既往歴を記入。 | 約10分 |
| 3 | 医師の診察・検査 | 医師との問診、血圧測定、体重測定、血液検検査(必要な場合) | 約10〜20分 |
| 4 | ピルの処方・薬の説明 | 薬の種類、副作用、服用方法などの説明。 | 約5〜10分 |
| 5 | 薬の受け取り | 院内処方の場合すぐに受取可能。院外処方の場合は近隣薬局へ移動。 | 約5〜10分 |
合計所要時間目安:約30〜60分
※病院の混雑状況や検査内容により所要時間は前後します。
低用量ピルの基礎知識
婦人科でピルを処方してもらう際に知っておきたい、低用量ピルに関する基本情報をわかりやすく解説します。
低用量ピルとは?
低用量ピルとは、女性ホルモン(エストロゲン・プロゲスチン)が含まれた飲み薬です。主に避妊を目的として使われますが、生理痛や生理不順の改善、月経前症候群(PMS)の緩和、子宮内膜症の治療目的としても広く使われています。
ピルには含まれる女性ホルモンの量によって、「低用量」「超低用量」「ミニピル」などの種類があります。中でも最も一般的に処方されるのが「低用量ピル」です。
【低用量ピルの主な使用目的と効果】
・避妊(避妊成功率99%以上) ・月経痛・生理不順の改善 ・子宮内膜症や月経前症候群(PMS)の症状軽減 ・ニキビや肌荒れの改善(ホルモンバランスの調整効果)
低用量ピルの種類と特徴
低用量ピルは、大きく「1相性ピル」と「多相性ピル」の2種類に分類されます。
| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット | 主な商品名(例) |
|---|---|---|---|---|
| 1相性 | ホルモン量が一定のタイプ | ・飲み間違えが少なく管理しやすい・月経周期調整に適する | ・不正出血が起こりやすい場合あり | マーベロン、ファボワール |
| 多相性 | ホルモン量が段階的に変化するタイプ | ・体のホルモン分泌に近く副作用が少なめ | ・飲み忘れた際の対応が複雑 | トリキュラー、アンジュ |
医師との相談の上、生活リズムや服薬管理能力に合ったものを選ぶのがベストです。
超低用量ピルとは
超低用量ピルは低用量ピルよりさらにホルモン量が少ないピルで、主に生理痛の軽減や月経困難症の治療目的で処方されます。ホルモン量が少ないため副作用が出にくいのが特徴ですが、一方で不正出血が多くなるケースがあります。
主な商品として「ヤーズ」「ヤーズフレックス」「ジェミーナ」などがあり、生理痛がひどい方や低用量ピルで副作用が強かった方に適しています。
ミニピルとは
ミニピルはプロゲスチン(黄体ホルモン)のみを含むタイプのピルです。エストロゲンが入っていないため、副作用の少なさが特徴であり、授乳中の女性やエストロゲンに対する副作用が出やすい人に処方されます。ただし、避妊効果を維持するには毎日同じ時間に正確に飲むことが必要です。
日本ではまだ取り扱いが少なく、主な商品には「セラゼッタ」があります。
【3種類のピルの違い早見表】
| 種類 | ホルモンの種類 | 避妊効果 | 副作用の程度 | 服用管理の難易度 | 主な処方目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低用量ピル | エストロゲン+プロゲスチン | ◎ | 中 | 易しい | 避妊・生理痛緩和 |
| 超低用量ピル | エストロゲン+プロゲスチン(低量) | ○ | 低~中 | やや易しい | 生理痛緩和・月経困難症 |
| ミニピル | プロゲスチンのみ | ○ | 低 | 難しい | 授乳中の避妊 |
それぞれ特徴を理解し、自分の体質や生活スタイルに合わせてピルを選びましょう。
ピル処方時の検査内容と診察の流れ
婦人科・産婦人科でピルを処方してもらう際には、簡単な診察や検査が行われます。具体的にどのような流れで行われるのか詳しく説明します。
問診票の記入
問診票はピルを安全に服用するために重要です。一般的に、以下の内容が問診票で確認されます。
【問診票の主な内容】
・氏名・年齢・住所・連絡先
・生理周期・生理痛の有無・月経量の状態
・妊娠歴・出産歴
・喫煙歴や飲酒量
・既往歴(高血圧、糖尿病、肝疾患、血栓症など)
・アレルギーの有無
・服用中の薬(他のピルを含む)
ピルを安全に服用するために、正確に記入しましょう。
血圧・体重測定
ピルを処方する際には、必ず血圧測定が行われます。これは、高血圧の人がピルを服用すると血栓症リスクが高まるためです。また、体重測定は、BMI(肥満度)の確認を目的として行われることがあります。
【注意すべき数値】
| 検査項目 | 問題となる数値の目安 | リスク |
|---|---|---|
| 血圧 | 収縮期140mmHg以上 | 血栓症リスクが高まる可能性あり |
| BMI | 30以上 | 副作用・血栓症リスクが高まる |
※上記の数値が当てはまる場合でも、医師と相談しながら服用できるピルを選択できます。
医師の診察(問診)
医師の診察は基本的に問診形式で行われます。婦人科でピルだけをもらいたい場合、内診は必ずしも必要ありません。医師との問診では、以下の内容を中心に確認されます。
- ピルを希望する理由(避妊、生理痛緩和など)
- 喫煙や生活習慣の確認
- 服薬経験やアレルギーの有無
問診は5〜10分程度で終了します。
初回処方時に必要な検査
初めてピルを処方される場合、必要に応じて血液検検査が行われることがあります。検査項目は主に以下の通りです。
【血液検査の主な内容】
| 検査項目 | 目的 |
|---|---|
| 肝機能検査(AST、ALT) | 肝臓の健康状態を確認するため。 |
| 血液凝固検査(Dダイマー等) | 血栓症リスクを事前に把握するため。 |
| 血糖値検査 | 糖尿病のリスクをチェックするため。 |
ただし、実際には血液検査を省略する医療機関も多く、健康状態に問題がなければ問診・血圧測定のみで処方されることがほとんどです。
定期検診の内容と必要性
ピル服用中は、半年〜1年に一度、婦人科で定期検診を受けることが推奨されています。これは、ピルの副作用や体調変化を早期に見つけるための重要な検診です。
【定期検診の主な内容】
・問診(服薬状況、副作用の有無を確認) ・血圧測定(毎回実施) ・血液検査(年1回推奨) ・必要に応じて子宮頸がん検診(年1回推奨)
日本産科婦人科学会も、ピル服用中は年1回程度の定期検診を推奨しています。
【検査・診察の流れまとめ】
| 診察時期 | 必要な検査・診察内容 | 所要時間の目安 |
|---|---|---|
| 初診時 | 問診・血圧測定・血液検査(必要時) | 約20〜30分 |
| 再診時以降 | 問診・血圧測定(血液検査は年1回程度) | 約10〜15分 |
定期検診を受けることで、ピルの安全性を高め、安心して服用を継続できます。
オンライン診療でピルをもらう方法
近年は婦人科を直接受診せず、スマホやパソコンを使ってピルを処方してもらう「オンライン診療」の人気が高まっています。この章では、オンライン診療を使ったピル処方の方法やメリット、注意点を解説します。
オンラインピル処方のメリット
オンライン診療の主なメリットは以下の通りです。
- 自宅で手軽に診察が受けられる
- 待ち時間がほぼない
- プライバシーが守られる
- 最短翌日に薬を受け取れる
オンラインピル処方の具体的な流れ
オンライン診療は以下の流れで行います。
①オンライン診療サービスを選び会員登録・予約
②予約日時にオンラインで診察を受ける(5〜15分)
③医師からピルの説明・処方
④自宅に薬が配送(翌日〜数日後)
※診察時に本人確認書類(保険証や免許証)が必要な場合あり。
オンライン診療サービスの選び方(料金・医師の対応・サポート)
オンライン診療サービスを選ぶ際には以下の項目を比較しましょう。
| 比較ポイント | 確認する項目 |
|---|---|
| 料金 | 診察料+薬代+送料の合計を確認 |
| 医師の対応 | 医師のプロフィールや患者の口コミ評価を参考 |
| サポート体制 | 副作用や飲み忘れ時のフォロー対応など |
| 配送スピード | 最短翌日配送〜数日以内に届くかどうか |
オンライン診療で注意したいポイント
オンライン診療の注意点は以下です。
- 初回は対面診療が推奨されるケースもある
- 正確な健康状態把握が難しいため、健康に不安があれば婦人科を直接受診することが望ましい
ピルの種類と選び方
ピルにはいくつかの種類があり、目的や体調、ライフスタイルによって適切なピルが異なります。ここでは、自分に合ったピルを選ぶために知っておきたい情報を解説します。
低用量ピルの種類と選び方
低用量ピルは女性ホルモンの配合によって大きく「1相性」と「多相性」に分類され、それぞれ特徴が異なります。
| 種類 | 特徴(配合の違い) | 向いている人の特徴 | 主な製品例 |
|---|---|---|---|
| 1相性 | ホルモン量が一定で飲みやすい | 飲み忘れが不安な人生理周期を調整したい人 | マーベロン、ファボワール |
| 多相性 | ホルモン量が周期で変化する | 副作用を抑えたい人自然なホルモン周期に近づけたい人 | トリキュラー、アンジュ |
ピル選びは医師と相談し、自分の体質や希望に合わせることが重要です。
保険適用ピル(LEP)の種類
ピルの中でも、保険適用で処方されるのがLEP(保険適用低用量ピル)です。避妊目的の場合は自費ですが、生理痛や子宮内膜症など、特定の病気治療目的の場合は保険が適用され、費用負担が軽くなります。
【保険適用ピルと自費ピルの比較】
| 項目 | 保険適用ピル(LEP) | 自費ピル(OC) |
|---|---|---|
| 使用目的 | 月経困難症、子宮内膜症の治療目的 | 主に避妊目的、生理周期の調整 |
| 費用目安 | 約1,000〜2,500円/月 | 約2,000〜3,500円/月 |
| 主な製品例 | ルナベル、ヤーズ、ジェミーナ | マーベロン、トリキュラーなど |
自分がどの目的でピルを使いたいかによって、医師と相談しながら選ぶのが良いでしょう。
アフターピルの種類と特徴
アフターピル(緊急避妊薬)は、避妊に失敗した時や、避妊ができなかった時に使用する緊急用のピルです。性交後72時間以内(理想は24時間以内)に服用することで、望まない妊娠を高確率で回避できます。
【主なアフターピルの種類】
| 種類(成分名) | 特徴・効果 | 避妊成功率(目安) | 服用期限 |
|---|---|---|---|
| ノルレボ錠(レボノルゲストレル) | 副作用が比較的少なく、安全性が高い | 約85〜95% | 性交後72時間以内 |
| エラ(ウリプリスタール酢酸エステル)※日本未承認 | 効果が高く、性交後120時間以内まで有効 | 約95〜98% | 性交後120時間以内 |
アフターピルは副作用も少なくありませんが、避妊に失敗した場合の緊急手段として婦人科で処方を受けることができます。最近ではオンライン診療での処方も増えています。
ピル選びで迷ったときのポイント
ピルの種類が多くて迷ってしまった場合、以下のポイントを参考にしてみましょう。
・避妊目的なら自費の低用量ピル(OC)
・生理痛や月経困難症の治療目的なら保険適用ピル(LEP)
・副作用を最小限に抑えたいなら超低用量ピルやミニピル
・服薬管理が苦手ならホルモン量が一定の1相性ピル
自分の目的に合わせて選び、婦人科で医師と相談しながら決定するのが安心です。
ピルの効果・メリットと副作用
婦人科でピルを処方してもらう前に、そのメリットと起こりうる副作用について理解しておくことが大切です。ここでは、ピル服用に伴う効果やメリット、デメリットを専門家の見解やデータを交えて解説します。
ピルの主な効果・メリット
ピルには避妊以外にも多くのメリットがあり、近年では月経トラブルの改善目的で使用する女性も増えています。
【ピル服用の主な効果・メリット】
・避妊成功率が高い(正しく服用すれば99%以上の効果)
・生理痛や生理不順の改善(月経困難症の症状軽減)
・月経前症候群(PMS)の症状軽減
・ニキビや肌荒れの改善(ホルモンバランス調整による)
・子宮内膜症や卵巣がんのリスク低下(長期服用による)
日本産科婦人科学会でも、低用量ピルの長期使用が卵巣がんの発症リスクを約40%低下させるという報告があります(2021年)。
ピル服用で起こりうる副作用・デメリット
ピルはメリットが多い薬ですが、初めて服用する場合、軽い副作用が現れる場合もあります。
【主な副作用と発生頻度】
| 副作用 | 発生頻度(目安) | 対処法・備考 |
|---|---|---|
| 吐き気、胃の不快感 | 約20~30% | 数週間以内に自然に治まることが多い。就寝前に服用すると軽減しやすい。 |
| 頭痛 | 約10~15% | 数週間以内に軽減。痛みが強い場合は医師に相談。 |
| むくみ、体重増加感 | 約10~20% | 軽度の場合が多く、継続で改善する場合が多い。 |
| 不正出血 | 約20~30%(特に服用開始初期) | 2〜3カ月で自然に減少するケースがほとんど。 |
服用を始めて1〜3カ月程度で副作用は軽減するケースが多く、辛い症状が続く場合は婦人科の医師に相談しましょう。
血栓症のリスクと兆候の見分け方
ピル服用で最も注意すべき副作用が「血栓症」です。血栓症は頻度としては低いものの、重大な副作用として知られており、特に喫煙者や肥満、高齢の方はリスクがやや高くなります。
【血栓症リスクの要因】
・35歳以上で喫煙している
・肥満(BMIが30以上)
・長時間の飛行機旅行や動けない状態が続く場合
・血縁者に血栓症の経験がある方
【血栓症の兆候(すぐに受診が必要な症状)】
・激しい頭痛や視力障害
・突然の胸の痛みや呼吸困難
・片足の腫れ、痛み、しびれ感
・吐き気・めまいが激しく続く
厚生労働省によると、低用量ピル服用者の血栓症発症率は年間約1万人に3〜9人程度と低頻度ですが、上記の症状が現れた場合はすぐに医療機関を受診しましょう。
副作用を抑えるための工夫
副作用の不安を軽減するためには、以下のような対策を行うと良いでしょう。
・吐き気がある場合は夜間や就寝前に服用する
・毎日同じ時間に服用し、ホルモンバランスを安定させる
・喫煙や過度な飲酒を避ける
・水分を十分に摂り、適度な運動を心がける
副作用が強く出る場合は、医師と相談の上、ピルの種類を変えることで改善することも多くあります。
ピルの費用と保険適用について
婦人科でピルを処方してもらう際、気になるのが費用面です。ピルには保険が適用されるものと自費診療となるものがあるため、それぞれの違いや費用の目安を事例やデータを交えて詳しく解説します。
保険適用となる条件
ピルには保険が適用されるタイプ(LEP)があります。ただし、保険が適用されるのは特定の治療目的の場合のみで、主に以下の症状に該当する場合です。
【保険適用の主な条件】
・月経困難症(重度の生理痛、生理不順など)
・子宮内膜症
・子宮腺筋症
上記の場合は保険適用ピルが処方され、費用負担が大幅に軽減されます。
【保険適用ピル(LEP)の費用例】
| 種類(薬名) | 1か月あたりの費用目安(保険適用後) |
|---|---|
| ヤーズ、ヤーズフレックス | 約2,000円~2,500円 |
| ルナベル配合錠 | 約1,000円~2,000円 |
| ジェミーナ | 約2,000円~2,500円 |
※3割負担の場合の一般的な目安です。
自費診療となる場合
一方で、主に避妊を目的としたピル(OC)は自費診療となります。これは日本では避妊目的の場合、ピルへの保険適用が認められていないためです。
【自費診療(OC)の費用目安】
| 種類(薬名) | 1か月あたりの費用目安(自費) |
|---|---|
| マーベロン、ファボワール | 約2,000円〜3,000円 |
| トリキュラー、アンジュ | 約2,000円〜3,500円 |
病院によって費用設定が異なるため、事前に病院のホームページや受付で費用を確認しておくことをおすすめします。
保険適用ピルと自費ピルの違い(メリット・デメリット)
保険適用ピルと自費ピルにはそれぞれメリット・デメリットがあるため、目的に合わせて選択する必要があります。
| 項目 | 保険適用ピル(LEP) | 自費ピル(OC) |
|---|---|---|
| 主な用途 | 月経困難症や子宮内膜症の治療目的 | 主に避妊、生理周期の調整目的 |
| メリット | 費用負担が少ない(保険適用) | 種類が豊富で選択肢が多い |
| デメリット | 種類が限定されている | 費用負担が大きい(自費診療) |
| 処方条件 | 医師の診断が必要 | 特別な診断は不要(医師との相談) |
費用を抑えるためのポイント
自費ピルの場合、費用負担が気になる方は以下の工夫を検討するとよいでしょう。
・ジェネリック医薬品を活用する(費用が安い)
・オンライン診療サービスの定期割引を利用する(数か月分まとめ買いで安くなる)
・自治体やクリニックのピル補助制度を調べる(例:自治体の女性向け医療費補助制度など)
最近では若い女性向けにピルの費用を一部補助する自治体もあり、各地域の制度を調べることで負担を軽減できます。
アフターピル(緊急避妊ピル)のもらい方と注意点
アフターピルは緊急避妊薬として、避妊に失敗した時などに婦人科やオンライン診療で処方してもらえる薬です。この章では、アフターピルの具体的な処方方法や注意点をまとめて解説します。
アフターピルの処方・相談時に怒られるって本当?
ネット上では「産婦人科 アフターピル怒られる」といった情報が見られますが、多くの医療機関では怒られるような対応はされません。ただ、一部で厳しい言葉をかけられたという事例もあるため、病院選びは重要です。
不安な場合は口コミを確認したり、女性医師のいるクリニック、オンライン診療サービスを選ぶことで心理的負担を軽減できます。
アフターピル処方時に怒られないためのポイント
怒られる不安を感じずスムーズに処方してもらうため、以下を参考にしてください。
【伝え方のポイント】
- 避妊ができなかった明確な理由(避妊失敗、コンドーム破損)を伝える
- 緊急性(性交後72時間以内の服用が必須)を医師に伝える
- オンライン診療を利用すると、心理的な負担が少ない
アフターピルの服用方法・効果
性交後なるべく早く服用することで、避妊成功率が高まります。
- 24時間以内の服用で95%以上の避妊効果
- 72時間以内の服用で75〜85%の避妊効果
国内で主に処方されるのは「ノルレボ錠」です。
アフターピル処方時の注意点
アフターピル処方時の主な注意点は以下の通りです。
- 副作用(吐き気、頭痛、不正出血など)に注意
- 嘔吐が服用2時間以内に起きた場合は再服用が必要になる可能性あり
- 緊急避妊用であり常用しないこと
- 避妊効果は100%ではないため、服用後3週間以内に生理が来ない場合は妊娠検査薬を使用
※オンライン診療でも処方可能です。
アフターピル服用後の注意点チェックリスト
服用後は以下の項目を確認して、体調変化に備えましょう。
・服用後の吐き気・嘔吐の有無を確認
・3週間以内に生理が来たか確認(なければ妊娠検査薬)
・副作用が強く出た場合の相談窓口を事前に調べておく
ピルの服用タイミングと正しい飲み方
婦人科で処方されたピルの効果を最大限に引き出すためには、正しいタイミングと飲み方が重要です。ここではピルの服用開始時期や、飲み方の基本を具体的に解説します。
飲み始めるベストなタイミング
ピルの飲み始めは、生理初日〜5日目までに開始するのが一般的です。この期間に服用を開始すると、飲み始めた初日から避妊効果が得られます。
【飲み始めのタイミング早見表】
| 飲み始め時期 | 避妊効果が得られるタイミング |
|---|---|
| 生理初日〜5日目までに服用開始 | 初日から効果あり |
| 生理6日目以降 | 服用開始から7日間は別途避妊が必要 |
ピルはいつから飲み始めても問題ありませんが、生理初日から5日以内の服用が最も推奨されます。
21錠タイプの服用法
21錠タイプのピルは、21日間連続で毎日1錠服用し、その後7日間の休薬期間を設けるタイプです。
【21錠タイプの飲み方】
- 生理初日~5日目までに飲み始める
- 毎日ほぼ同じ時間に1錠ずつ服用
- 21錠すべて飲み終えたら7日間休薬
- 休薬期間の8日目から次のシートを開始
休薬期間中に月経が起こる仕組みです。
28錠タイプの服用法
28錠タイプのピルは、21錠の実薬と7錠の偽薬(プラセボ)がセットになっています。偽薬は飲み忘れを防ぐための薬で、ホルモン成分は入っていません。
【28錠タイプの飲み方】
- 生理初日~5日目までに飲み始める
- 毎日同じ時間に1錠服用(実薬→偽薬の順で28日間)
- 偽薬服用中に月経が来る
- 偽薬が終わったら翌日から次のシートを開始
28錠タイプは毎日服用習慣がつくため、飲み忘れが心配な人に向いています。
飲み忘れたときの対応
ピルを飲み忘れた場合は、以下の対応を参考にしてください。
| 飲み忘れた日数 | 対応方法と注意点 |
|---|---|
| 1日(24時間以内) | 気づいた時点で直ちに1錠服用し、その日の分も通常通り飲む(1日2錠) |
| 2日以上連続 | 服用を中断し、次の生理を待って新しいシートを開始。その間は他の避妊方法を使用 |
※飲み忘れ後は約1週間、避妊効果が低下するため、コンドームなど他の避妊手段が必要になります。
2シート目以降のもらい方とタイミング
2シート目以降は、初回処方時にまとめて複数シートもらうか、オンライン診療を利用して薬を自宅配送してもらうことも可能です。1シート終了の約1週間前を目安に、次回の薬を準備するのがおすすめです。
【2シート目以降の受取方法】
・病院でまとめて処方(通常2〜3シート)
・オンライン診療を利用して定期的に受け取る(定期配送サービス)
多くの人は2〜3ヶ月ごとにまとめて処方を受けています。定期診察(半年〜1年に1回)を受けながら継続することが一般的です。
ピル服用後の体の変化と妊娠への影響
婦人科で処方されたピルを服用後に起こる体の変化や、将来的な妊娠への影響を解説します。ピルを安心して使うために、服用終了後の体調変化や妊娠に関する正しい情報を確認しておきましょう。
服用終了後の体の変化
ピルの服用を終了すると、多くの場合、2〜3か月以内に自然な月経周期が再開します。ただし、人によっては月経が不規則になったり、生理痛が再発することもあります。
【ピル終了後によくみられる変化】
・月経周期が不規則になる(一時的)
・月経量や生理痛が元に戻る(ピル服用前の状態に近づく)
・ニキビや肌荒れが再発する可能性がある
・ホルモンバランスの変化で体調が不安定になることも
実際には多くの人が1〜3ヶ月以内に安定しますが、長期的に生理不順が続く場合は婦人科で相談しましょう。
将来的な妊娠への影響
ピルを服用すると将来的に妊娠しにくくなるという誤解がありますが、実際には影響はほぼありません。WHO(世界保健機関)や日本産科婦人科学会も「ピル服用が将来の妊娠能力に影響することはない」と明確に示しています。
【ピル服用後の妊娠に関するデータ】
| 項目 | 内容・根拠 |
|---|---|
| ピル服用終了後の妊娠確率 | ピル中止後1年以内に約80〜90%が妊娠(WHO報告) |
| ピル服用年数と妊娠成功率 | 服用年数が長くても妊娠能力への影響はない(日本産科婦人科学会) |
実際、ピルを中止すると排卵が再開し、早ければ1〜2ヶ月以内に妊娠可能な状態に戻ります。妊娠を望む場合、服用終了後はすぐに妊活を始めても問題ありません。
定期検診の必要性・がん検診の推奨
ピルを服用中、定期検診は非常に重要です。ピル自体は安全な薬ですが、副作用や身体の変化を早期に見つけるため、半年〜1年に1回の定期検診が推奨されています。
【定期検診で行われる主な検査】
・問診(服薬状況・体調の確認)
・血圧測定、体重測定
・血液検査(肝機能・血栓症のリスク評価)
・子宮頸がん検診(年1回推奨)
特にピルを服用する女性は定期的な子宮頸がん検診が推奨されています。これはピルが子宮頸がんのリスクを多少高める可能性があるためで、定期的に検診を受ければ早期発見・早期治療が可能です。
【子宮頸がん検診の推奨頻度】
・20歳以上の女性は2年に1回(厚生労働省の推奨)
・ピル服用中は1年に1回程度が望ましい
定期的な検診を受けることで、ピル服用中も安心して健康管理ができます。
未成年・高校生のピル処方のポイント
近年、未成年や高校生がピル処方を希望するケースが増えています。しかし、「産婦人科 ピルだけもらう高校生」など、実際に婦人科を訪れる前に不安を感じる方も多いでしょう。ここでは未成年が婦人科でピルをもらう際の具体的な流れや注意点を解説します。
高校生がピルをもらう具体的な流れ
高校生でも多くの場合、婦人科・産婦人科でピルを処方してもらえます。具体的な流れは以下の通りです。
【高校生が婦人科でピルをもらう流れ】
①病院の情報収集(ネットの口コミや公式サイトをチェック)
②予約(オンラインまたは電話)
③問診票の記入(生理の状況、服薬経験、健康状態など)
③医師との問診(約5〜10分)
④薬の選択・処方
③薬を受け取る(院内処方または薬局で受取)
特に未成年の場合は病院ごとに対応が異なるため、事前確認が重要です。
未成年がピルをもらう際の注意点(親の同意は必要?)
未成年(20歳未満)がピルを処方してもらう場合、多くの医療機関では親の同意書や保護者の同伴を求めることがありますが、同意が必要ない病院も増えています。
【未成年者の親の同意要否の例】
| 医療機関の対応 | 同意の有無 | 具体的な対応例 |
|---|---|---|
| 同意書必須の病院 | 必要 | 保護者の同意書(HPでダウンロード可能) |
| 一定年齢以上なら同意不要の病院 | 不要(条件付) | 16歳以上なら同意書不要のクリニックも多数 |
| オンライン診療(特に最近増加) | 不要の場合多い | 本人確認書類提出、電話確認のみ |
事前に各病院のホームページや電話で、「未成年ですが、ピルの処方に親の同意は必要ですか?」と確認しておくことが安心につながります。
未成年へのピル処方の実際(事例)
実際に高校生のピル処方について、次のような事例があります。
【ケース①:17歳高校生・東京都在住】
「生理痛が辛く親にも相談できず、ネットで調べて親の同意が不要な婦人科を受診した。問診後すぐに低用量ピルを処方された。」
【ケース②:高校2年生・地方在住】
「ピル処方には親の同意書が必要で、親に相談したが理解が得られなかった。その後オンライン診療を利用し、同意書なしで処方を受けることができた。」
こうしたケースもあるため、事前のリサーチが大切です。
未成年がピルを服用する際の注意点
未成年がピルを服用する場合、特に気をつけるべきポイントは以下です。
・副作用(吐き気や頭痛など)について事前に理解し、服用を継続できるよう準備しておく。
・正しい飲み方や飲み忘れ時の対処法を医師に詳しく確認する。
・緊急時や副作用が強い場合に相談できる窓口(クリニックの電話相談、LINE相談など)を把握しておく。
親に知られたくない場合でも、オンライン診療や保護者の同意不要の病院を選ぶことで安心して処方が受けられます。
ピルのよくある質問(FAQ)
婦人科でピルを処方してもらう際に、多くの女性が気になる疑問についてQ&A形式でまとめました。具体的なデータや専門的な意見を交えながら回答します。
Q1:ピルは通販で買える?
A. 日本国内でピルを通販購入することは薬機法で禁止されています。
低用量ピルやアフターピルは医師の処方箋が必要な医薬品(要処方医薬品)のため、正規のオンライン診療や婦人科・産婦人科の対面診療でのみ処方が可能です。
海外サイトから個人輸入する方法がありますが、厚生労働省は「品質や安全性が保証されないため推奨しない」と警告しています。必ず医療機関やオンライン診療サービスを利用しましょう。
Q2:診察にかかる時間はどれくらい?
A. 初診の場合、診察から薬の受け取りまで約30〜60分が一般的です。
【婦人科診察の平均的な所要時間目安】
・問診票記入:約5〜10分
・医師の問診・検査:約10〜15分(血圧・体重測定など)
・薬の処方・説明:約5〜10分
・薬の受け取り(院内または薬局):約5〜10分
2回目以降は短縮され、約10〜20分程度で終了します。
Q3:未成年でもピルを購入できる?
A. 未成年(高校生含む)でもピルの処方は可能ですが、病院によっては親の同意書が必要になることがあります。
全国の婦人科の約半数以上が未成年へのピル処方を実施していますが、親の同意については対応が分かれます。
- 親の同意書不要の病院:約30~50%程度
- 親の同意書必須の病院:約50~70%程度(地域差あり)
※厚生労働省の調査結果(2022年)より推定
親の同意書を得にくい場合は、親の同意が不要な病院やオンライン診療を利用すると安心です。
Q4:未成年でも購入できる?
A. 未成年でもピルは処方してもらえますが、親の同意が必要な病院もあります。
日本の法律では未成年でもピルの処方は可能ですが、未成年の場合、親の同意を求める病院が多くあります。親の同意なしで処方を受けたい場合は、婦人科に電話で確認するか、未成年向けのオンライン診療サービスを利用するとスムーズです。
また、未成年の場合、オンライン診療では同意書なしで処方可能なサービスが多いため、そういった方法を検討するのもおすすめです。
【未成年のピル処方方法の比較】
| 方法 | 親の同意の有無 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 婦人科(対面) | 必要な場合あり | 医師の丁寧な説明を直接聞ける | 病院によって同意書が必須の場合あり |
| オンライン診療 | 不要が多い | 誰にも知られず処方を受けられる | 保険適用がないため費用負担が増える |
未成年でも安心して処方を受けるために、自分の状況に合わせて方法を選びましょう。
ピル処方を婦人科で受ける前に知っておくべきポイント(まとめ)
婦人科でピルを処方してもらうことは決して難しいことではありません。この記事では「婦人科でのピルのもらい方」をテーマに、具体的な処方方法や種類、オンライン診療の活用法まで幅広く解説しました。最後に婦人科でスムーズにピルを処方してもらうための重要なポイントを整理しておきます。
婦人科でピルをもらうためのポイント
- 初診時には問診・血圧測定など簡単な検査がある
- 未成年者は親の同意書が必要な場合と不要な場合があるため、事前確認が必須
- オンライン診療を活用すれば、忙しい方や周囲の目が気になる方も安心
- 避妊目的は自費診療、月経困難症や病気の治療目的の場合は保険適用が可能
- 副作用(血栓症など)に注意し、定期的な検診(半年~1年に1回)を受けることが推奨される
- ピル服用後の妊娠能力に悪影響はない
初めてピルをもらう人のための受診準備チェックリスト
以下のチェックリストを参考にして受診準備を行いましょう。
- 病院の口コミやホームページを確認した
- 初診時にかかる費用の目安を調べた
- 未成年の場合、親の同意書が必要か確認した
- 生理周期や体調に関する情報をメモした(問診票用)
- 副作用や飲み方で気になる点を事前に整理した
自治体のピル費用助成制度を利用する
最近ではピルの費用負担を軽減するため、自治体が女性を対象とした助成制度を実施している地域もあります。例えば東京都や大阪府など一部地域では、若年層のピル購入費用を助成しています。お住まいの自治体でこうした制度が利用できるか事前に調べておくと、経済的な負担を抑えることができます。